2月のようす
2月27日(火曜日)
なわとび大会がありました。今回は、雨の日が多く練習が思うようにできない日もありましたが、
ペアの学年で休み時間などを利用しながら練習に取り組んでいる姿がありました。
競技の面もありますので、記録により表彰も行いましたが、それよりは、
今回のとりくみを通してできた「つながり」を大切にしてほしいと思います。
これからの学校生活の中でも、今回の「つながり」をいかして、いろんなことに
挑戦していってほしいと思います。
また、お昼休みには、図書ボランティアの方がたが、折り紙教室を開催してくださいました。
たくさんの子どもたちが参加し、会場となった図工室はいっぱいになっていました。
今回は、パンダなど動物を折り紙で作っていたようです。
子どもたちも笑顔で、とても楽しい時間となったことだと思います。


2月26日(月曜日)
今日は午前中に、来年度1年生として日新小学校に入学してくる子どもたちを対象に
体験入学を実施しました。
少しでも小学校の様子を体験できればと実施していますが、この間コロナ禍の影響もあり
久しぶりの開催となりました。
現在の1年生とペアになり体育館から教室まで案内し、本読みの様子を見てもらったり、
グループに分かれて折り紙などを体験しました。
入学まであと約1か月。子どもたちと一緒に活動できる日が楽しみです。
2月23日(金曜日)
本日、泉佐野市立文化会館レセプションホールにおいて、第12回あのねフェスティバルが
開催されました。その中では、あのね文庫詩コンクールの表彰式もありました。
本校からも、コンクールに応募し、4名の子どもたちが入賞し、本日表彰を受けていました。
どの子の作品も、自分の想いを素直に表現した良い作品でした。
2月21日(水曜日)
この間5年生では、識字教室についての学習を行ってきました。
さまざまな理由で小学校などに通うことができず、学習ができなかった方がたに対して、
文字を学ぶ場所として今現在もある教室です。
今日は、実際に教室のある北部市民交流センターに行き、識字教室で講師をされている方から
お話を聞きました。
識字教室に通われている方の想いを交えながら、お話をしてくださいました。
子どもたち一人ひとりが、とても集中してお話を聞いていたように感じました。
現在、当たり前のように学べる環境にある自分たちにとって、今日のお話を受け止め、
どのようなことができるかを考え、行動にうつしていってほしいと思います。
また、どうして識字教室が必要な状況があったのかにも考えを深めることができればと思います。
今回の聞き取り学習は、第三中学校区の三つの小学校合同で行いました。
本校は、新池中学校に進学する子どもたちもいますが、中学校になった時、
一緒に過ごす仲間との出会いの場でもありました。
来年度は、中学校の体験入学の時にも一緒に活動を行うことになります。
互いの交流を深めるようなこともできればと思います。

2月20日(火曜日)
5年生が調理実習を行っていました。
何をつくっているのかとのぞくと、白玉団子をつくっていました。
粉を練り、丸めてからゆでて団子にしていました。
きれいな丸い形に仕上げている班や少し大きさにばらつきがある班など、
形は様々でしたが、班員みんなで協力しながら、楽しく作っている様子が大変ほほえましく思えました。
自分たちで作ったものですから、とてもおいしかったのではないかと思います。


2月16日(金曜日)
6年生の中学校進学に向け、今日は、給食センターから中学校での給食についてのお話に
来てくださいました。
小学校での給食と中学校での給食の違いなどについてお話していただきました。
配膳のやり方や食管の違い、さらには、使っている器の大きさが大きくなることなどが
ありました。写真を見て比べているときなどは、器の大きさの違いから、
量が少なくなっているとの意見も出ていました。しかし、一人当たりに
配られる量は、今よりも少し多くなるとのことでした。
体も大きく成長する時期だと思います。バランスよく食べて健康に過ごしてほしいと思います。

2月13日(火曜日)
2年生では、聴覚に障害のある方からのお話を聞かせていただきました。
普段の生活で困ることやそれを克服するための工夫などたくさんのことを
聞かせてくださいました。
クイズなども交えながら、子どもたちも興味を持ちながら聞けたと思います。
また、お話の中に、「デフリンピック」についてのことがありました。
あまり聞きなれないことですが、聴覚に障害がある方たちを対象にしたオリンピックだそうです。
「パラリンピック」は、世界的にもよく知られていますが、「デフリンピック」は、まだまだ
知らない方も多いと思います。オリンピックと同じように4年1度開催されているとのことです。
次回は、2025年に東京で開催されるそうです。このことが一つのきっかけとなり、
多くの人に知ってもらうことができたらと思います。
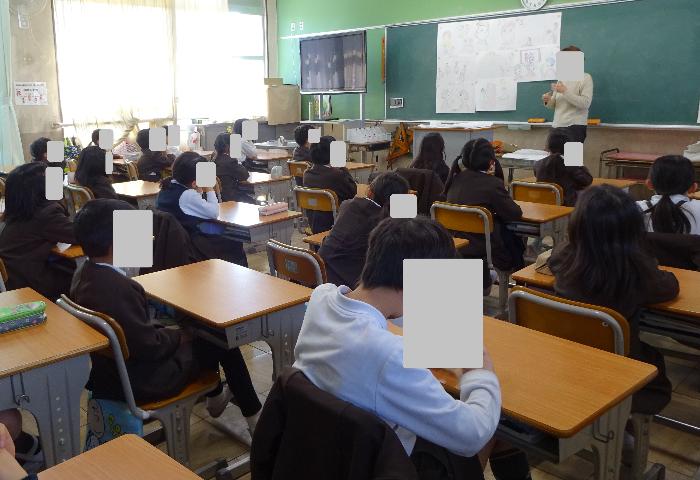
お昼休みには、図書ボランティアの方がたが、お話の会を開いでくださいました。
毎回楽しいお話を読み聞かせしてくださっています。
子どもたちも、興味津々でお話に夢中になっていました。
次回は、2月27日(火曜日)に折り紙教室を開いてくださる予定です。
今から楽しみです。

5時間目には、6年生に向けて新池中学校、第三中学校の先生方が来てくださり、中学校生活に向けてのお話をしてくださいました。
それぞれ進学予定の中学校に分かれ、お話を聞かせていただきました。
行事や学習面についてのお話、校則についてのお話など、子どもたちにとって、
中学校進学に向けて、気持ちの準備をしていくうえでとても有意義な時間に
なったことだと思います。

2月8日(木曜日)
全体でのなわとび運動の第2回がありました。
前回は、ペアの学年との顔合わせが主でしたが、今回は、ペアでの練習、
そして、第1回目の計測を行いました。
練習では、学年が上の子どもたちが、見本を見せたり、声をかけたりしながら、
学年が下の子どもたちがうまく飛べるようにとがんばっていました。
下の学年の子どもたちも、アドバイスを聞きながらチャレンジをしていました。
計測もあったので、記録も気になるところではありますが、子どもたちには、
ペアでの練習の中から、多くのことを感じ、学び取ってほしいと思います。
休憩時間にも、ペアで練習している姿を見かけます。全体でのなわとび運動の時間だけではなく、
休み時間などのペアでの練習を通して、成長してほしいと思います。

2月7日(水曜日)
2年生は、国語科で「スーホーの白い馬」の学習をしています。
モンゴルの民族楽器である馬頭琴がつくられたもとになるお話です。
今日は、その学習に絡めて、現在モンゴルから国際交流員として泉佐野市に来られている方から、
モンゴルの習慣や生活の様子などについてお話しいただきました。
子どもたちは、国語科で学習したこともあり、とても興味を持ちながら、
お話を聞いていたように思います。
また、民族衣装を着させていただいたり、実際の馬頭琴に触れさせていただいたりと、
学びを深めていくとてもいい学習になったと思います。
最後には、モンゴルのじゃんけんについて教えていただき、実際に講師の方とじゃんけんを
楽しんでいました。


2月6日(火曜日)
本日の授業参観に、たくさんの保護者のみなさんがご参加いただき本当にありがとう
ございました。
今回4年生では、泉佐野市の危機管理課の方をお招きし、防災についての学習を行いました。
その中で、参観いただいた保護者のみなさん間と一緒に、避難経路を考えたり、
防災リックの中身を考えたりと、災害に備えることについて考えていきました。
災害は、いつ起こるかわかりません。日ごろから、起こった時どのようにするのかなどについて、
考えておくことが大切だと思います。
今回は、風水害のことについて考えましたが、地震が起こった時のことなどについても
考えておく必要があると思います。ぜひ、今回のことを一つの機会ととらえ、
ご家族で災害が起こった時の行動などについてお話していただければと思います。


2月3日(土曜日)
本日第10回SANOリンピックが泉佐野市立総合体育館で開催されました。
泉佐野市内の小学校4年生から6年生の子どもたちがなわとびの飛べた回数を競います。
前一重とび、後一重とび、前交差とび、前あやとび、前二重とびの5種目が行われます。
子どもたちは、この中から2種目をエントリーすることができます。
本校からも13名の子どもたちが参加しました。緊張の中、子どもたちは、一生懸命に
参加をしていたように感じます。
競技を終えた後は、大阪体育大学ダブルダッチ部のみなさんによるダブルダッチ演技を披露して
いただくとともに、子どもたちもグループに分かれ、教えてもらっていました。
他の小学校の子どもたちと触れ合う機会にもなり、終わった後は、話をしている様子も
見られました。


2月2日(金曜日)
なわとび運動が始まりました。高学年と低学年でペアを組み、一緒になが縄の練習を通して、
相手を思いやる気持ちを育てていくことを目標にしています。これから、約1か月の間、
休み時間等を使いながら練習を行っていきます。飛んだ回数で一喜一憂するのではなく、
ペア学年で、高学年は低学年を教える中でのかかわり方や飛べるようになっていくことの喜びを
感じてほしいと思います。
また、低学年は、高学年の人たちから教えてもらう活動を通して、自分たちが今後高学年に
なった時のことも考えながら、先輩のようすからたくさんのことを感じ取ってほしいと思います。
また、午後からは、5年生が、谷口病院の谷口先生を講師に迎え、命の大切さについての学習を
行いました。様々な幸運が重なり誕生する一つの命、この世に一つしなかない大切な命。
実際に医療の現場でお仕事をされている先生の言葉から、子どもたちも命の大切さを
感じ取ることができたのではないかと思います。
命の大切さを感じ、自分を大切にすること、そして、周りの人を大切にすることを
これからも行動に移していってほしいと思います。









更新日:2024年02月27日